ラボニュース | Kids プログラミングラボ
ラボニュース
LAB NEWS



新着記事
-
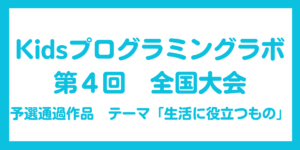
イベント
Kidsプログラミングラボ 第4回全国大会
予選通過作品 テーマ「生活に役立つもの」2023.11.14
-
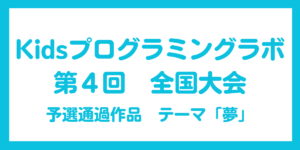
イベント
Kidsプログラミングラボ 第4回全国大会
予選通過作品 テーマ「夢」2023.11.14
-
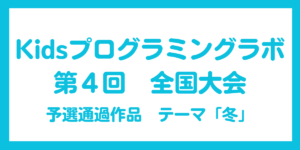
生徒の活躍
Kidsプログラミングラボ 第4回全国大会
予選通過作品 テーマ「冬」2023.11.14
-

ジュニア・プログラミング検定
\合格率9割超*/ 教室ならではのジュニア・プログラミング検定対策。3つの「合格ポイント」
2023.10.20
-
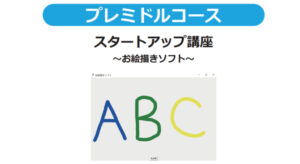
アドバンスコース
Scratch(スクラッチ)からPython(パイソン)、その先へ。教室で本格プログラミング言語への進級準備をする「スタートアップ講座」
2023.09.22
-
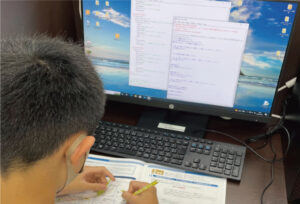
プレミドルコース
本格言語「Python(パイソン)」プログラミングを教室で無料体験しませんか?
2023.08.25
-

FC教室加盟
【FC教室紹介】IT企業ならではの地域貢献を。講師自ら楽しみ、生徒とともに成長中
2023.06.23
-

FC教室加盟
【FC教室紹介】加盟わずか5カ月で、2教室目オープン。 地域の子が安心して集う場づくりを
2023.05.30
-
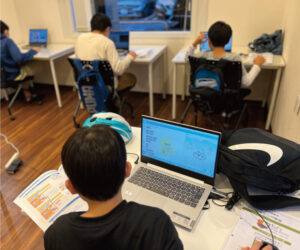
プライマリーコース
【プライマリーコース】教室で遊んで慣れるプログラミング! Scratch(スクラッチ)に夢中になる理由3
2023.05.24
-

ベーシックコース
【ベーシックコース】教室で楽しくプログラミング。Scratch(スクラッチ)ゲーム教材の魅力って?
2023.04.10
-

FC教室加盟
【プログラミング教室フランチャイズ運営】本部の「見えない」サポートも確認を
2023.03.10
-
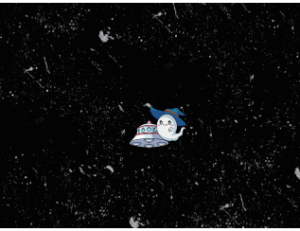
無料体験会
プログラミングスクールの体験。作るゲームって、どんな感じ?
2023.02.14
-

ジュニア・プログラミング検定
【スクール講師が解説】ジュニア・プログラミング検定では「国語力」も大切
2023.01.20
-

イベント
【2022年秋】プログラミングの楽しさ伝える、子ども向けキャラバンを開催!
2022.12.23
-
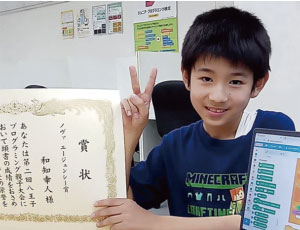
生徒の活躍
Kidsプログラミングラボ生徒、Scratch(スクラッチ)作品で入賞
2022.12.23
-
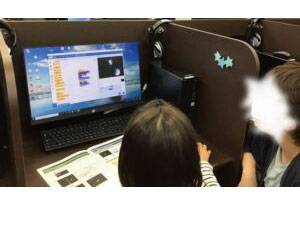
イベント
【開催レポ】小学生・中学生女子プログラミング体験会「KIKKAKE-ガールズプログラミングフェス」
2022.12.16
-

学校教育支援
児童が前のめり!小学校【英語×プログラミング】の学習相乗効果
2022.12.16
-
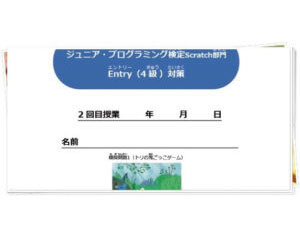
ジュニア・プログラミング検定
【スクール講師に聞いてみた】ジュニア・プログラミング検定、合格の3ポイント
2022.12.16
-

オンライン授業
【お困り解消クリニック】プログラミングのオンライン授業、トラブル解決!
2022.12.16
-

無料体験会
【小学生・中学生 プログラミング教室】無料体験会レポート
2022.12.16